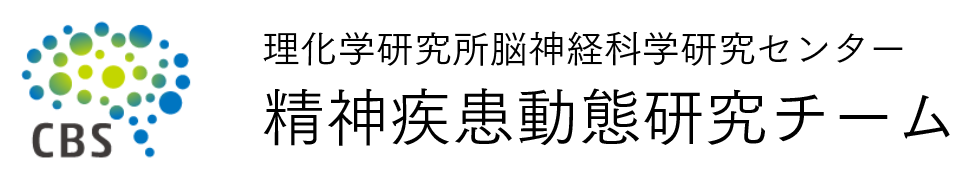- Home
- 連携講座
2018年4月に理化学研究所脳神経科学研究センター(理研CBS)が発足すると同時に、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻に、この脳機能動態学連携講座が発足し、理研CBS精神疾患動態研究チーム・チームリーダーの加藤忠史が、この連携講座の教授を兼任し、大学院生の指導等に当たることになりました。
研究内容
当研究室では、双極性障害の神経生物学的な研究を行っています。
実は私は、学生時代以来、「心の物質的基盤とは何か」を探求したいと考えてきました。その考えは、今も変わった訳ではありませんが、実際にはこの問いはあまりに茫漠としていて、答えようがありません。
精神科の臨床研修を行ううち、双極性障害の患者さん達に出会い、こんなに困っている人がいて、科学・技術が進んでいるにもかかわらず、精神疾患に全く科学のメスが入れられていない現状を目の当たりにしました。そして、精神疾患の中でも、多くの方が困っていて、最も明瞭な症状を呈し、脳の変化が明らかな疾患である双極性障害の解明を目指し、現在に至っています。
双極性障害の原因を解明することができれば、診断法・治療法の開発につながることはもちろん、「感情の物質的基盤とは何か」という問いにも答えることができると考えています。
双極性障害の最大の謎は、なぜゲノムを基盤とする疾患なのに、躁とうつという両極端な症状が出現するのか、ということです。この謎を解き、新たな診断法、治療法の開発に繋げるべく、ゲノム解析、死後脳解析、動物モデル・細胞モデルを用いた解析などを進めております。
特に、双極性障害を高頻度に伴うメンデル型遺伝病であるミトコンドリア病に着目した研究により、作成したミトコンドリア病の中枢神経症状の動物モデルが、二週間程度の低活動状態を自発的に反復するという行動変化を示すことを見出し、これが人における抑うつエピソードに相同なものであることを示し、双極性障害に似た治療反応性を示すことがわかりました。
このマウスにおいて、変異ミトコンドリアDNAが蓄積している部位を探索した結果、視床室傍核に変異が最も蓄積していました。視床室傍核の神経細胞の神経伝達を回路遺伝学的手法で遮断すると、同様のエピソードが現れることから、この部位が双極性障害の原因である可能性を考えています。現在、この部位に着目して、基礎と臨床をつなぐべく、動物モデルを用いた更なる解析に加え、患者死後脳における解析などを進めています。
現在の精神医学では、診断は心理学的評価に頼っており、治療も1950年前後に偶然に近い形で発見された薬の改良版に止まっており、原因分子を標的としたものではありません。もし、精神疾患が特定の神経細胞の病変によるものであることがわかれば、精神医学の次の地平が見えてくるはずだと期待しています。また、もし躁・うつが特定の神経回路の病変によって生じることがわかれば、その神経回路は元々気分を安定させる機能を持っていたと考えられ、気分の神経生理学という、新たな研究の方向性を指し示すものにもなりうると考えています。
研究室の特色
- 1) 基礎と臨床をつなぐ研究
-
精神疾患は、まだ原因解明が進んでいないため、動物実験だけで解明できる状況ではありませんが、臨床研究でできることも限られています。そのため、基礎研究と臨床研究を有機的につなぐ研究が必要と考えています。
- 2) 網羅的解析と仮説検証を組み合わせた研究
-
精神疾患では、山ほど仮説があり、候補遺伝子研究では擬陽性所見ばかりが出てしまったという経緯があり、網羅的解析が必要です。しかし、多量のデータから仮説を構築し、検証するというプロセスもまた重要です。当研究室では、網羅的解析と仮説検証をバランス良く組み合わせた研究を志しています。
- 3) データ駆動型サイエンスと実験の組み合わせ
-
さまざまなデータベースが整備された現在、実験だけで論文を構築するよりも、こうしたデータを活用して解析することにより、より意義ある結論が導き出せるようになっています。当研究室では、こうしたデータ駆動型の研究と実験の組み合わせ、成果を最大化することを目指しています。もちろん、当研究室のデータも広く公開しています(GSE12649、GSE12654等)。
- 4) 最先端技術の活用
-
新たな科学的発見は、多くの場合、新たな技術によってもたらされます。当研究室では、理化学研究所という場を活かし、さまざまな共同研究を通して、最先端の研究技術を取り入れています。
- 5) 国内外の幅広い共同研究ネットワーク
-
日本からインパクトの高い研究成果が少ないのは、共同研究が少ないからではないか、という説があります。当研究室では、国内の多数の研究者との共同研究を進めると共に、海外の多くの研究室とも共同研究を進めてきました。例えば、自閉症研究の第一人者であるDaniel Geshwind教授(UCLA)、バイオインフォーマティクスのMichael Oldham准教授(UCSF)、遺伝学のFrancis J. McMahon氏(NIMH)およびJohn Kelsoe教授(UCSD)、エピジェネティクスのMichael Meaney教授(ダグラス病院)など、多くの海外の研究者との共同研究論文を発表してきました。また、国際コンソーシアム(ConLiGen, Bipolar Seqnencing Consortium)にも参加しています。
沿革
理研CBSの前身である理化学研究所脳科学総合研究センター(理研BSI)は、元々、東京大学医学部長を務められた伊藤正男先生を初代所長として1997年に設立されました。伊藤先生は、東大時代に感じた全ての課題を克服できるような研究所としてBSIを設計されました。研究室主宰者(PI)及び全ての研究者の約2割は外国人で、公用語は英語。研究者が研究に専念できるように必要な装置とスタッフを備えた研究基盤センター、任期制研究者のみで構成され、PIが退職するとその研究室は解散という流動的運営など、当時としては斬新な設計は、その後、甘利俊一第二代センター長、利根川進第三代センター長にも継承され、20年のBSIの優れた業績の土台となりました。
こうして、理研BSIは、東京大学と並ぶ、日本における脳科学の研究拠点となりましたが、BSIの創立後20年以上が経過し、世界情勢も大きく変わりつつあります。我が国の人口減少、新興国の台頭などから、もはや東大と理研が密接に連携しないと、日本のプレゼンスを示せない時代と言えましょう。
平成30年3月に、理研BSIは20年の歴史を終えることになりましたが、その折に、日本に脳研究の拠点が必要であるという、神経科学研究コミュニティーからの強い後押しによって、理研CBSが誕生しました。そして、東京大学大学院医学系研究科機能生物学専攻の教授でいらっしゃった宮下保司先生がセンター長に就任され、東大と理研CBSの連携の枠組みを作られました。その中で、東大医学系研究科に理研CBSとの連携講座を2講座設立すると同時に、理研CBSにも東大医学系研究科との連携チームを作り、基礎と臨床をつなぐ研究を推進していくという方向に決まりました。こうした連携の一環として、加藤忠史が東京大学医学系研究科機能生物学専攻脳機能動態学連携講座教授を拝命しました。
加藤忠史 略歴

| 1988年 | 東京大学医学部医学科卒業 |
|---|---|
| 1989年 | 滋賀医科大学附属病院精神科助手 |
| 1995~1996年 | 文部省在外研究員としてアイオワ大学精神科にて研究 |
| 1997年 | 東京大学医学部精神神経科助手 |
| 1999年 | 東京大学医学部精神神経科講師 |
| 2001年 | 理化学研究所脳科学総合研究センター精神疾患動態研究チーム チームリーダー |
| 2015~2018年 | 同センター 副センター長 |
| 2018年 | 理化学研究所脳神経科学研究センター 精神疾患動態研究チーム チームリーダー(現職) |
| 2018年 | 理化学研究所 脳神経科学研究センター 研究基盤開発部門長(現職) |
| 2018年 | 東京大学医学系研究科機能生物学専攻脳機能動態学連携講座教授(現職) |